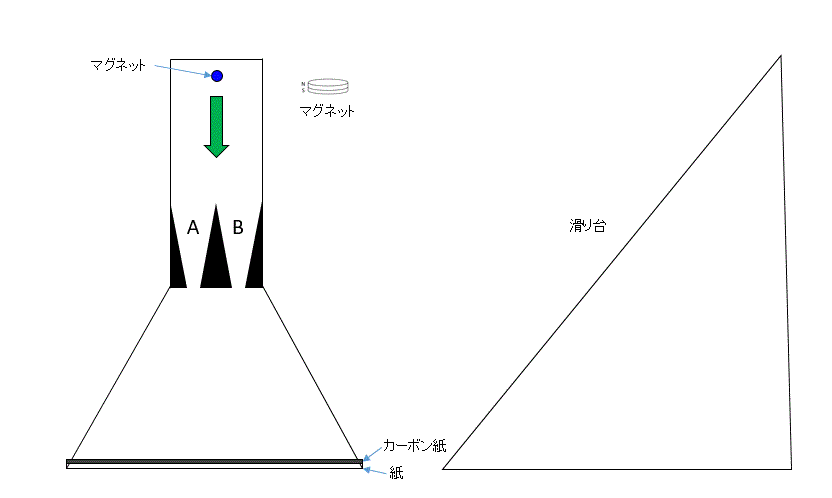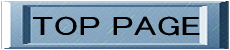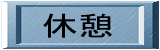皆さんは、「シュレーディンガーの猫」というパラドックスをご存知でしょうか?
半死半生の猫が現れたり、観測結果が時間を逆上って原因に影響を与えたり、SFのパラレルワールド(多世界解釈)、夜空に浮かぶ月は、誰も見ていないとそこには存在していない。
などなど、たくさんの面白い話が出てきます。
しかし、私には、半死半生の猫や誰も見ていなければ月は存在しないなんて、どうしても受け入れられなかったのです。
これらのことを否定するのは誰にでも出来るが、否定するにはそれなりの根拠が必要と考え、
「シュレーディンガーの猫」について、自分流に解釈した結果をまとめてみたものです。
あくまでも自己満足かもしれないけど、興味ある人は読んでみてください。
9.2 シュレーディンガーの猫
まず、シュレーディンガーの猫について簡単に説明する。
フタ付きの鉄の箱の中に、放射性元素、放射性元素崩壊を検知する検知器、その検知器に連動して動作するハンマー、毒ガス入りのガラスびん、猫を入れておく。
仕掛けとしては、放射性元素崩壊すると、それを検知器が検知してハンマーが作動して毒ガス入りのガラスびんを割る。するとその毒ガスによって猫は死ぬ。
ここで、放射性元素崩壊は1時間に50%の確率で起きるとする。
ただ、これだけの装置である。
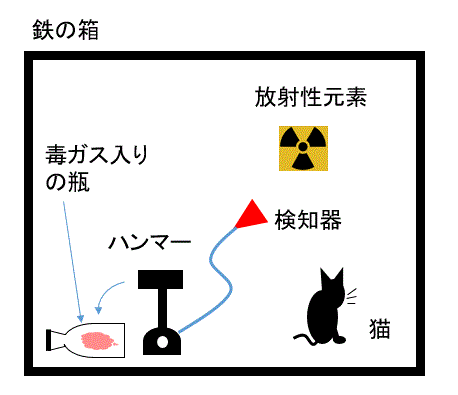
では、問題です。
この装置を準備し、鉄の箱のフタを閉めて中が見えないようにする。
1時間後にフタを開けて猫を観測したら猫はどうなっているか?
答えな簡単だ。
猫は生きているか、死んでいるかのどちらかで、その確率はどちらも50%である。
そう、それは正しい。異論を唱える人はいないだろう。
では、フタを開ける直前に猫はどうなっていると思いますか?
な、なんと、量子力学の考え方を延長すると、フタを開ける直前まで、猫は半死半生の状態を保っているのである。
これは、瀕死状態の猫という意味ではなく、生きている猫と死んだ猫の2つの状態が共存しているということである。
そして、フタを開けて観測した瞬間に、猫は生か死のどちらかの状態に決定するというのだ。
一般常識からすればれば、フタを開ける直前には、すでに猫の生死は決まっているよね。
ところが、量子の世界では、「重ね合わせ」とか言われる不思議な現象があるのだ。
量子力学なんてミクロの世界の話であり、マクロの世界で起こる現象とは違うという意見もあるが、
この「シュレーディンガーの猫」の装置は、ミクロの世界で起きたことがマクロの世界にまで連動して起きる装置である。
だから、マクロの世界もミクロの世界と同様ことが起きていると考えられるのである。
この摩訶不思議な思考実験を考案したシュレーディンガーさんは、「フタを開ける直前の箱の中には半死半生の猫がいる」と言っているわけではなくて
「半死半生の猫なんているわけ無いだろう。」だから、量子力学は、不完全な理論だということを言いたかったみたいだが、
シュレーディンガーさん本人も、生きている間にその不完全な部分を指摘することができなかった。
こんな不思議な話が出てきたのには原因がある。
それは、あの有名な二重スリット実験である。
9.3 二重スリット実験
二重スリット実験については、Youtubeに、とてもわかりやすい動画があるので、まずはそちらを見ていただきたい。
https://www.youtube.com/watch?v=vnJre6NzlOQ
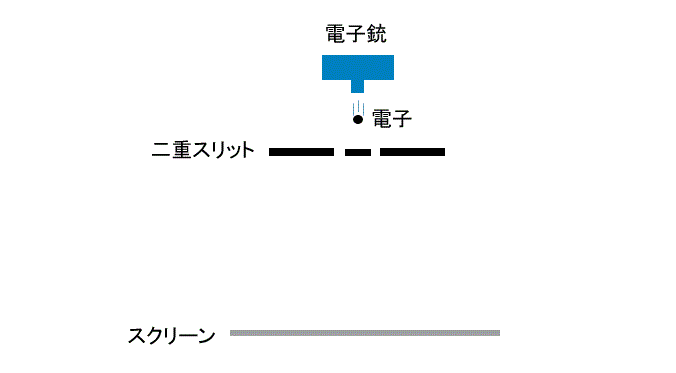
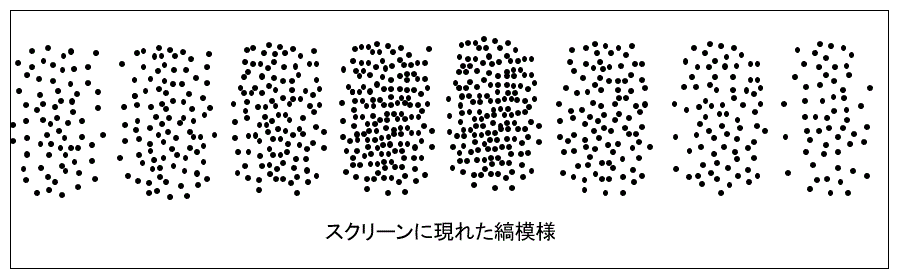
この二重スリット実験の結果については、何度も検証されているので、疑いようのない事実と考えられる。
この実験で使われた電子は、量子の一種であり、量子は分割できなのである。
電子は分割できないのに、2つのスリットを同時に通過したような振る舞いをするのである。
ならば、電子がA、Bどちらのスリットを通過したのかを調べようとスリットの出口にセンサを設置すると、スクリーンに干渉縞がなくなった。
電子を検出するためには、光などを電子に当てて検出する必要がある。
その時の光が電子の軌道に影響を与えた結果、干渉縞が消えたんだと思われた。
そこで、電子の軌道にほとんど影響を与えない弱いマイクロ波を使って電子の検出を試みたのだが、結果は、光を当てた時と同じように干渉縞は消えてしまった。
電子はまるで意思のを持った生き物のようである。観測されていることを察知しているのか?
と、「観測問題」に発展する。
観測問題についてはさておき、電子が2つのスリットを同時に通過することに対して、現在の量子力学的な解釈では、
電子は、粒子と波動(平たく言えば”波”)との2つの性質をもっており、「電子は波となって2つのスリットを通過した。」となる。
と、ここまでは、教科書通りです。
これ以降は、持論になるので、話半分に読んで頂ければ幸いです。
9.4 電子は粒子か波か
現在の量子論では、電子は粒子と波の2つの性質を持っているとされている。
持論を展開する前に、皆さんは”波”と言ったら何を思い浮かべるであろうか?
池に石ころを投げ入れたときに起きる”波紋”。
空気の振動の波である”音”。
それら、水面にできる波や音だって、もとをたどれば水分子や空気分子ではないか。
つまり、「たくさんの粒子が集まれば”波”の性質を持つんだ。」と言いたい。
砂粒だって、大量の砂粒をイメージすれば、互いにぶつかり合って干渉し、波のように振る舞うことは想像できると思う。
ここで、皆さんからは、1つの疑問が聞こえてくる。
「電子は、たった1つだよ。これでは波の性質をもつことの説明ができないよ。」と。
それに対する私の回答はこうだ。
「電子は、たった1つでも、たくさん集まった電子の集団として振る舞う。」
なぜ、そんな考えに達したかについて説明する。
頭を柔らかくして、イメージしてもらいたい。
今、あなたは、一人で広場の中央に立っている。
ここで、力いっぱい真後ろにジャンプしてみてほしい。
何か起こりましたか?
「何も起きなかった。?」
ははーん。ジャンプ速度が足りませんね。
もっと、速くジャンプしてみて下さい。
まだ、何も起きない?
では、光の速度よりも速く後方にジャンプしてみて下さい。
どうですか?
自分の背中が見えたはずです。
どうしても自分の背中が見えなかった人は、SFアニメ「宇宙戦艦ヤマト」のワープシーンを思い出してほしい。
ヤマトが地球の大気圏を出た直後に月の周回軌道上にワープする場面を考える。
地球から月までの距離は、約38万kmだから、光の速度で約1.3秒かかる。
ヤマトがワープに成功した直後、地球の方向を見たときに、地球の方向にはまだヤマトが見えることになる。
光より速く移動したのだから、光が後から遅れてやってくるのである。
では、今度は、あなたは電子になってもらいます。
同様に、後方に光の速度よりも速くジャンプしてみて下さい。
今度は、何が起きましたか?
電子は、マイナスの電荷を持っているのです。
だから、ジャンプした直後、前方にいるあなた(電子)と反発して後方に跳ね飛ばされたはずです。
電界が作用する速度より速く移動したため、電界による反発力が時間差をおいてやって来たのである。
今度は、ランダムな方向にジャンプを繰り返してみて下さい。
あなた(電子)の周囲は、あなた(電子)で埋め尽くされているはずです。
そう、これが、たった1つの電子が電子の集団をつくるメカニズムです。
ランダムな方向へ瞬間移動を繰り返す。
更に、滞在時間もどんどん短くして、究極の”0”にしてみよう。
つまり、実際に存在している時間も”0”、移動時間も”0”だ。
どうです。1個の電子が、3次元空間に薄く広がって、煙のように見えてきませんか?
もし、目で見ることができたら、中心か濃くて、中心から離れるほど薄くなっていると思う。
これって、教科書にも出てくる「電子雲」のイメージそのものです。
注意点として、電子の集団と言っても、電子がたくさんあるわけではなく、薄く広がっているだけなので、
電子雲全体の電荷の総量は、1粒の電子と同じである。
量子力学では、「電子の存在確率」などと表現をするが、これは、観測したときに1粒の電子として出現する場所の確率のことで、
電子が雲の中のどこかにいるというより、1つの電子が薄く広がって分布していると考える方がイメージは近い。
実際には、この雲状の電子は、波を打って振動しているのかもしれないが、この後の話には影響がなのので、深堀りはしないことにする。
二重スリット実験で大量の電子を二重スリットに向けて打ち出せば、スクリーンには干渉縞が現れることがわかっている。
電子が1粒の粒子ではなく、ある大きさを持った雲の塊で、電子の集団のように振る舞うのなら、二重スリット実験の結果もそれほど不思議な現象ではない。
つまり、2つのスリットの幅がその雲の塊の狭けれれば、2つのスリットを同時に通り抜けることが出来るのではないかと考えたのである。
電子の雲が2つのスリットを同時に通り抜けるイメージ図を下に示す。
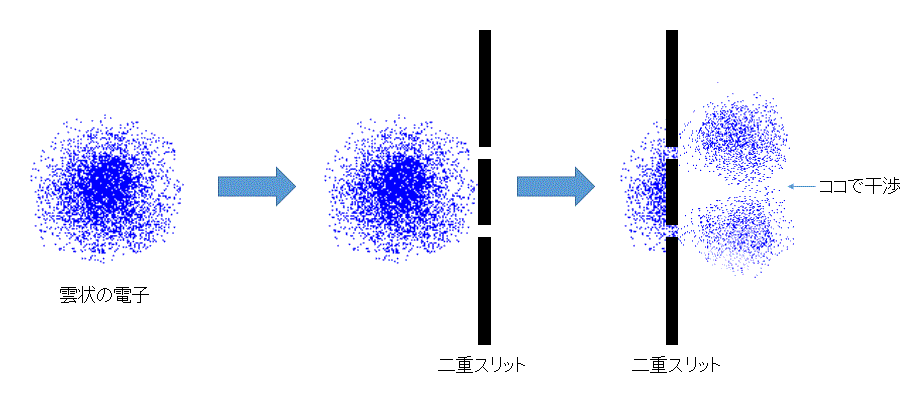
あるいは、片方のスリットを通り抜けた電子が二重スリットの前方からの(自分の)電界波の影響を受けているとも考えられる。
電界は壁も通り抜けるが、壁越しの電界波は、電界作用に遅れが生じるため、二重スリットの何らかの影響は受ける筈である。
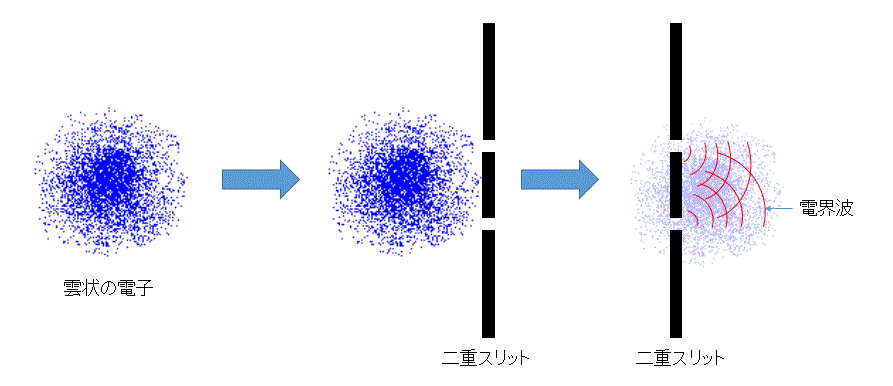
9.5 光速を超えるための条件
と、ここまで読んで頂いたところで、「光の速度を超える」というところに疑問を持つ人がいると思います。
相対性理論から考えて、光の速度を超えることは不可能だと。
それに対して私は、「光の速度を超えることは、条件付きで可能である」と考える。
その条件は2つあるが、まずその1つ目の条件について説明する。
確かに、相対性理論によると、質量のある物体を加速していくと、質量が増す。
そうして、光の速度に達すると、質量は無限大になる。
だから、無限大の質量の物体は、どんなに大きな力で加速してもそれ以上加速できなくなる。
つまり、光の速度とは究極の速度であり、それを超えことはできない。
ところが、これは、物体を加速して速度を上げていく場合である。
加速を伴わない物体の移動なら、質量増加による速度限界は存在しないのである。
光の速度を超えると言ったが、むしろ、消えた瞬間に別の場所に現れる瞬間移動と言った方がイメージは近い。
そして、もう1つの光速を超える条件とは、「情報を持たない」ことである。
では、情報とは何か?
一言で言うと「情報とは変化である。」となる。
例えば、津波発生を知らせるサイレンがあったとする。
サイレンが鳴った。
これも、今まで「サイレンが鳴っていない」状態から「サイレンが鳴った」という変化である。
では、サイレンが一定の音量、一定のトーンで、ずっと鳴り続けていたらどうだろうか?
これでは、津波発生を知らせることができない。
つまり、音に何らかの変化がなければ情報伝達はできないのである。
サイレンの音が大きくなったとか、トーンが変わったとか、音色が変わったなどの変化があってこそ、津波発生の情報を伝達できるのである。
「電子は情報を持っていないから光速を超えられるのだ」と言いたいところだが、電子そのものが情報である。
ちょっと矛盾しているように思われるが、このことについての詳しい説明は後述することにする。
その前に、何故情報を持っていると光速を超えられないかについて説明したいと思う。
9.6 情報が光速を超えられない理由
情報が光速を超えられない理由、つまり光速を超えた通信ができない理由について述べたいと思う。
答えを先に言ってしまうと「因果律崩壊を防ぐため」となる。
このことを説明するためには、相対性理論に登場してもらう必要がある。
相対性理論によると、同時刻というものが、見る人の立場によっては、同時刻ではなくなるのです。
わかりにくいので、例をあげます。
登場人物は3人で、それぞれA君、B君、C君とし、3人は友人とします。
現在は、2020年7月21日とします。
A君は前日(2020年7月20日)から、現在(2020年7月21日)まで、ずっと東京の自宅にいました。
B君は、この日(2020年7月21日)自家用車で東京から箱根方面にドライブに出かけています。
C君は、地球から遙か彼方をロケットで宇宙旅行をしていました。(ちょっと、C君だけぶっ飛んでますけど)
C君は、遠くのものを瞬時に見ることが出来る特殊な望遠鏡を持っていたとします。
信じられないかもしれませんが、その望遠鏡でA君とB君を見た時、C君と地球との距離、ロケットの速度(光速以下でいい)、飛行する方向によっては、
2020年7月20日のA君と2020年7月21日ドライブ中のB君が同時に見えるのです。
これは、A君とB君からの映像がC君に届くのに時間差があって同時に見えるのではなく、C君にとっては、2020年7月20日自宅にいるA君と
2020年7月21日にドライブ中のB君は同時刻に進行している事象なのです。
C君がこの特殊望遠鏡でB君を見ているときに、B君が自動車事故を起こして、B君は命を落としてしまいました。
なんとかしなければと考えたC君は、2020年7月20日のA君に連絡を入れます。
連絡を受けたA君は、同時刻(2020年7月20日)を生きているB君に2020年7月21日に起きる自動車事故のことを知らせます。
知らせを受けたB君は2020年7月21日の箱根ドライブをキャンセルし、B君は一命をとりとめることができました。めでたしめでたし。
このような話は、SF映画などではよく題材になります。
タイムマシンで過去に行って、自分の両親を殺したら、自分が消える?
そもそも、自分が存在しないなら、両親を殺すことはできない。
原因があるから結果があるのであって、結果が原因に影響を与えてしまうと、この世は無秩序の世界になってしまいます。
この宇宙の秩序を保っているのは、因果律であり、因果律こそが絶対法則なのである。
しかし、光より速い情報伝達手段があったら、この因果律を崩壊させてしまうことになります。
そこで神様は、因果律崩壊を防ぐために、情報伝達に299792458m/sec(約30万km/sec)という速度の限界を与えたのだと思う。
光の速度が絶対というより、神様が決めた299792458m/secという情報伝達絶対速度は、光をもってさえ超えられないということではないだろうか。
先の話では、通信速度が有限なために、A君がC君から連絡を受けたときには、B君が自動車事故を起こした後ということになる。
余談になるが、「量子もつれ」など量子のもつ不思議な性質を利用して、超光速通信の実用化を目指す試みがあるようだ。
私の考えでは、どんなに装置を工夫したところで、因果律という絶対法則がある以上、この試みは失敗すると思われる。
これは、歴史的にみて、永久機関の開発に似ている。
様々に工夫を凝らした装置が考案されたが、すべて失敗に終わっている。
その理由は、装置の問題ではなくて、根源に「エネルギー保存の法則」があり、どんなに装置を工夫しても永久に仕事をさせることは無理だったのである。
9.7 電子が情報を持ったら
さて、電子は、光の速度を超えて瞬間移動すると仮定したが、これは、明らかに速度超過で、神様が決めたルールに反している。
このルールは量子というミクロの世界でも適用されなければならない。
では、瞬間移動する電子が情報媒体になるかについて考察してみる。
話を簡略化して、電子がA地点とB地点の2点間を瞬間移動を繰り返しているとしよう。
量子力学的には、A地点に電子が存在している確率は50%、B地点に電子が存在している確率も50%である。
電子は分割できないけど、A地点、B地点にそれぞれに50%同時に存在していると言ってもいい。
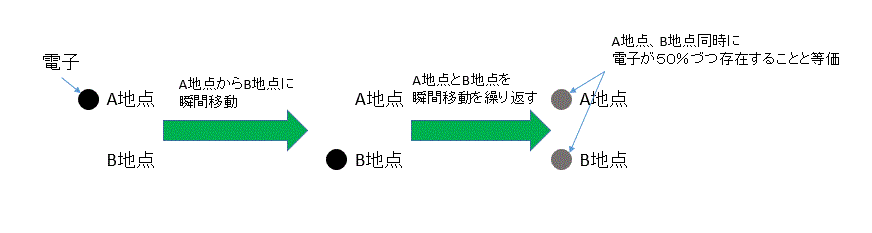
この定常状態において、A地点からB地点に何か情報を伝えているかと考えると情報は何も伝えていない。
情報を持っていないから、超光速瞬間移動が出来るとも言える。
そこで、電子が瞬間移動する能力を利用してA地点からB地点に情報を伝えることを試みてみる。
例えば、A地点にいる電子にペンキで赤色をつけてみよう。
すると、瞬時にB地点に赤色の電子が現れ、光の速度を超えた情報伝達ができそうである。
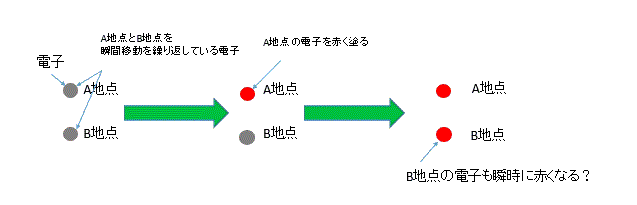
ところが、そうはならない。
電子を赤色に塗った瞬間に電子は変化したことになる。
変化は情報であり、情報は、光の速度を超えられないのだ。
実際に何が起こるか想像してみると、A地点の電子にペンキで赤色に塗った瞬間にB地点に存在していた50%の電子は消滅し、A地点に100%の赤い電子だけが現れる。
雲状だった電子が、一瞬にして粒子になる瞬間である。
(この現象って、量子力学で言うところの「波動関数の収縮」のことではないだろうか。)
赤くなった瞬間の電子は、どのような状態かというと、粒子として出現したというより、おそらく同じ場所で瞬間移動は繰り返している状態ではないだろうか。
人間で言えば、ランダムに飛び回っていた状態から、その場で足踏みしている状態である。
二重スリット実験で、電子を観測するためにエネルギーの弱いマイクロ波を使った事例を紹介したが、電子の軌道に影響を与えないくらい弱いエネルギーだったのに電子の重ね合わせは消滅した。
これは、観測のためのマイクロ波照射が電子に僅かではあるが(運動量の)変化を与えてしまったからではないだろうか。
どんなに些細な変化であっても変化は変化である。
つまり、マイクロ波を照射された電子は、情報を持ってしまったのである。
宇宙戦艦ヤマトで例えれば、ヤマトの艦内に1通の小さな手紙を忍ばせただけで、ヤマトはワープはできなくなるのである。
では、その後はどうなるか考えてみると、光の速度で伝達出来る範囲のワープは、因果律を崩壊させないので神様も許してくれる。
具体的には、ヤマトの艦内に1通の小さな手紙を忍ばせてから、1.3秒後には月までのワープが可能、数分後には火星程度の距離までのワープが可能になる。
電子の状態で考えてみると、1点に収束していた電子が、光の速度で広がっていって、もとのある大きさの雲の塊に戻る。
言い方を変えると、電子は観測しているときは「粒子」、観測していないときは「波(雲状)」となる。
電子は、見ているとそこに存在しているのに、見ていないと場所が特定できない。
これって「不確定性原理」にも通じるように思える。
電子は、意思を持っていない。だから、見られていることを察知しているのではない。
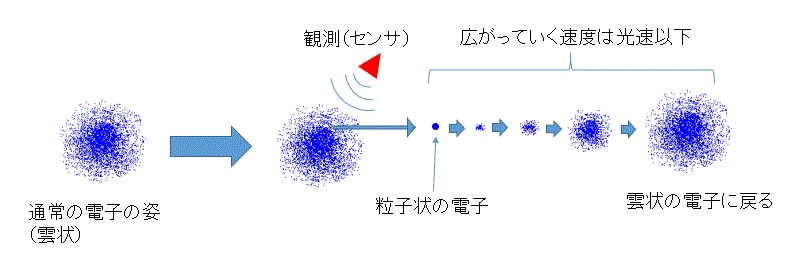
9.8 自分流シュレーディンガーの猫
何故、シュレーディンガーさんは、あのような装置を考案したのだろう。
量子の重ね合わせの不思議さを表現するために、もっと直接的な装置を考えてみよう。(下図)
二重スリット実験装置の2つのスリットの出口にそれぞれ電子を検出するセンサを設置する。
そのセンサの信号の先には、2つのピストルが設置され、電子の検出に連動してピストルの引き金が引かれる。
ピストルの銃口の先には、A、B2匹の猫がいる。
(ちょっと残酷だけど、思考実験だから許して下さい。)
電子銃から電子を1個だけ発射する。
スリットを通り抜けられず、跳ね返される電子もあるけど、電子がスリットを通り抜けた場合だけを考えることにする。
スリットを通り抜けた電子は、センサで検知され、センサに連動して動くピストルの引き金を引いて、その先の猫が死ぬ。
このとき、フタを開けて箱の中を確認するまでは、2つの状態が重ね合わせになっている。
本来は、「Aの猫の死とBの猫の死、が重ね合わせになっている」と言うべきである。
半死半生の猫という概念は、この現象の半分を切り取ったものだ。
つまり、Aの猫だけに注目し、Aの猫が死んだ状態と生きている状態という重ね合わせにすり替えられていることに注目したい。
この装置でも、箱を開ける直前まで、半死半生の猫がいる。
そして、フタを開けた直後にA,又はBの猫の死が決定する訳である。
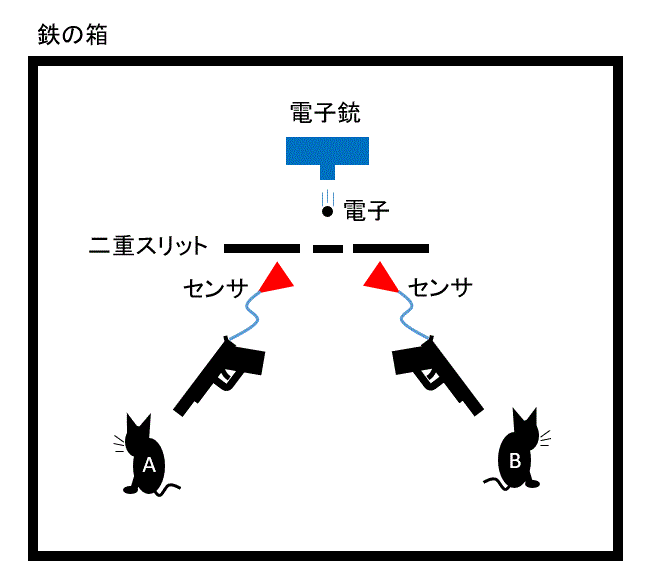
でも、ちょっと待って下さい。
この装置には欠陥があることに気づきましたか?
センサ!
そうです。電子を検出するセンサです。
二重スリット実験でのところでも説明しましたが、スリットにセンサを設置して、電子を検知しようとすると、干渉縞は現れないのだ。
電子の存在を観測した瞬間に「重ね合わせ」は解消される。
具体的には、電子がどちらかのセンサに検知された瞬間に反対側の電子は消滅することになる。
ミクロからマクロへの連動は、このセンサの部分で断ち切られているのである。
9.9 シュレーディンガーの猫の核心
そろそろ、シュレーディンガーの猫の核心に迫ってみたいと思う。
本家の「シュレーディンガーの猫」の装置を見直したのが下の図である。
1時間に50%の確率で放射性元素の崩壊が起こるのだから、平均すると2時間に1回の割合で放射性元素の崩壊が起こることになる。
放射性元素の崩壊は、不規則に発生する現象なので、4、5時間放射性元素の崩壊は起こらない場合もあるが、その確率は小さいので、話を簡略化するために
2時間に1回放射性元素の崩壊が起きると仮定しよう。
装置をセットして箱のフタを閉めて箱の中が見えないようにする。
放射性元素の崩壊を検出するセンサの出力には、タイマ式の切り替えスイッチが設置されており、フタを閉めた直後はAの猫に向けられたピストルの引き金信号となっているが、
1時間後にタイマが作動してBの猫に向けられたピストルの引き金信号となる。
2時間後、フタを開けて箱の中を確認する直前では、Aの猫の死とBの猫の死が重ね合わせの状態になっている。
本家のシュレーディンガーの猫装置は、この装置の前半の1時間だけを切り取り、Aの猫だけに注目し、放射性元素が崩壊する場合と崩壊しない場合の「重ね合わせ」としている。
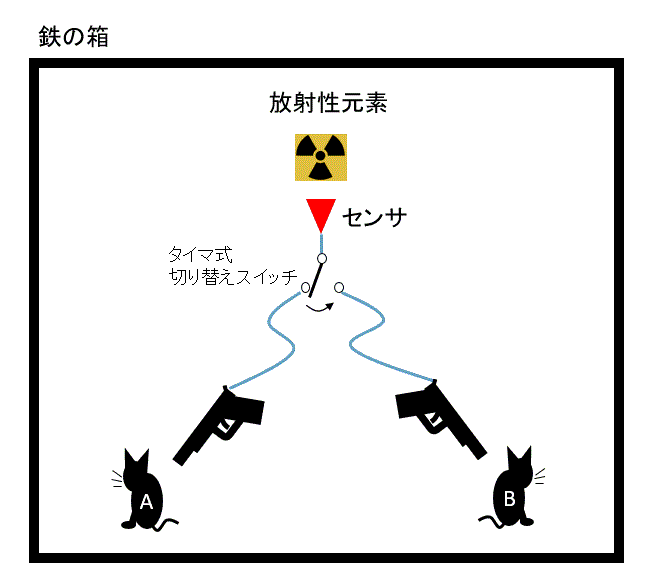
ちょっと、おかしくないですか?
私は、重ね合わせという現象は、電子が雲状になっていることに起因していると考えた。
つまり、重ね合わせは、あくまでも空間的な話であり、時間的な話ではないと思っている。
だとしたら、空間的なものである「重ね合わせ」が、時間軸に対して「重ね合わせ」とした最初の出発点から間違っていた事になる。
つまり、1時間以内に放射性元素の崩壊があったら、猫は死ぬ。その確率は50%。ただそれだけのことである。
観測という行為が放射性元素の崩壊に影響を与えていないのなら、観測するしないには関係ないし、フタを開ける直前にはすでに猫の生死は決定している。
これが、シュレーディンガーの猫に対する私の答えである。
「重ね合わせ」という言葉が、独り歩きした結果、半死半生の猫を出現させてしまったのではないだろうか。
ちなみに、放射生元素の崩壊を検知する検出器がありますが、このセンサは、放射性元素の崩壊を検出しているだけで、
放射性元素の崩壊には影響を与えていないので、ミクロからマクロへの連動には無関係である。
9.10 まとめ
ここで、私がイメージした世界をまとめておくことにする。
通常、1つの電子は、ランダムな方向への瞬間移動を繰り返すことで、3次元空間に煙のように薄く広がった状態(雲状)で存在している。
だから、電子の正確な位置を特定できないのは当然で、これが「不確定性原理」のもとになっている。
雲状だから「重ね合わせ」という奇妙な状態が存在してしまうことになる。
無数の電子の集合体だから、無数の重ね合わせが存在する。
電子を検出しようとして、光などをこの雲状の電子に照射すると、電子は(運動量の)変化を受ける。
変化とは、情報であり、情報は光速を超えられない。そのため、僅かであっても変化を受けた電子は瞬間移動できなくなり、霧が晴れたように1つの粒子として姿を表わす。
これが、「波動関数の収縮」である。
量子力学では、存在確率という表現をするが、これは、観測した瞬間にある場所に現れる確率のことで、雲状の電子では、薄いけれど△%の電子がそこにあると考える。
例えば、雲状電子を上下1/2に分けると、下半分には電子の50%、上半分にも電子の50%が実際に存在していることになる。
電子は分割できないのに、無数の(薄い)電子の集団として3次元空間に分布している。
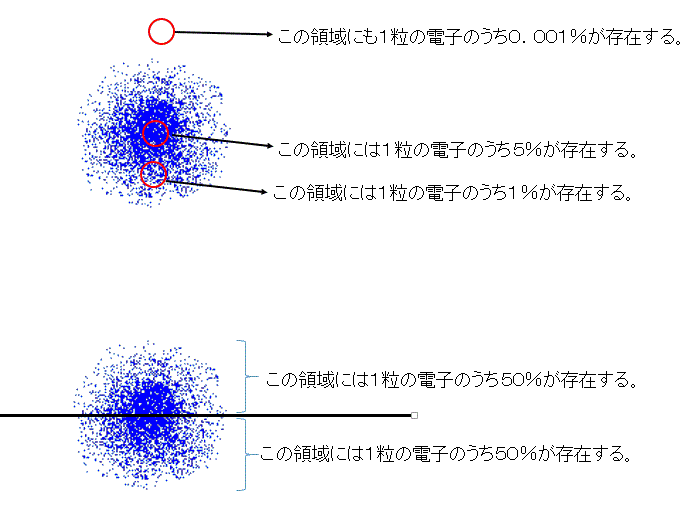
9.11 ミクロとマクロの境界
今まで量子の代表選手である電子について考察を進めてきたが、
実は、電子以外にも炭素分子のフラーレンでも二重スリット実験でスクリーンに干渉縞が現れることが知られている。
フラーレンのひと粒は、目に見えないので、我々にとっては十分にミクロな存在ではあるが、電子から見れば、とてつもなく大きな存在である。
フラーレンの二重スリット実験で干渉縞が現れるなら、パチンコ玉くらいの大きさのものだって、2つのスリットを通り抜けられてもおかしくない。
だって、ミクロとマクロに境界なんてないんだ。
だから、月だって誰も見ていなければ、2つのスリットを同時に通り抜けられる筈だ。
と考える人もいるだろう。
しかし、ミクロとマクロには境界があるのだと思う。
ミクロとかマクロの定義にもよるが、二重スリット実験で2つのスリットを同時に通り抜けられるものをミクロ、
2つのスリットを同時に通り抜けられないものをマクロとするなら、
二重スリット実験で2つのスリットを同時に通り抜けられるものと、そうでないものがあると思うのだ。
ミクロとマクロを分ける1つ要因は、その物体を構成する原子や分子が変化しているかどうかである。
大きな物体は、それを構成する原子や分子の数が多い。
だから、大きな物体は、常に一部が変化している確率が高くなる。
故に、変化は情報であるため、常に変化していれば、瞬間移動はできないことになる。
できないと言うより、できる可能性は限りなく小さいと言える。
さらに、瞬間移動出来る距離が数μmだとすれば、パチンコ玉が数μm瞬間移動を繰り返したところで、ほとんど位置が変わらない。
写真で例えるなら、電子は元の大きさより何倍も大きくピンボケした写真で、フラーレンより大きな分子は、輪郭がぼやけたピンボケ写真といったところであろうか。
パチンコ玉くらいの大きさになると、輪郭のばやけもほとんど見えない。
実体の大きさより2倍以上大きくピンボケ出来る物体のみ、二重スリット実験で干渉縞を残せる可能性がある。
(ピンボケの大きさって、あまりはっきりした大きさではないけど)
故に、大きな物体は、二重スリットで2つのスリットを同時に通り抜けることはできないと言うより、その可能性は限りなく0(ゼロ)に近い。
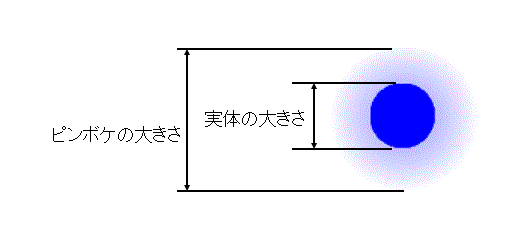
9.12 観測問題
私の考えでは、観測問題とは、電子が観測者から見られたことを察知しているのではく、(光などを照射する)観測という行為が電子に変化を与えることに起因する現象である。
しかし、頑なに夜空に浮かぶ月は、誰も見ていないと位置は特定されないと思っている人も多いようだ。
そこで、こんな実験を提案したい。
滑り台を用意して、途中の通路をA、Bの2つに分ける。
滑り台の下にカーボン紙とカーボン紙に抱き合わせた紙を設置しておく。
滑り台の上方からコイン型のマグネットを滑らせながら落とす。
マグネットは、裏表がS/Nになっているものを使う。
このマグネットは、反発する電子の代わりである。
マグネットは、滑り台を滑って行き、最後にカーボン紙に衝突して、その後ろの紙に衝突痕を残す。
これを繰り返して実験する訳だが、途中の経路に覆いをして、マグネットがA、Bのどちらの経路を通ったかわからないようにする。
認めたくはないけど、もしも、この実験を数百回繰り返した後、紙に残った衝突痕に干渉縞が現れたら、
マグネットは、人が見ていなければ、波となってA、B同時に通過したことを認めるしかありませんね。